コツをつかんで楽しむ表裏~雑俳『物者附』の魅力その①~ [web雑俳]
江戸言葉遊び・雑俳の一つ『物者附』。
題に沿った物事を「裏」に隠し、それとはできるだけ意味の離れた「表」を詠むという遊びです。
題に沿った物事を「裏」に隠し、それとはできるだけ意味の離れた「表」を詠むという遊びです。
もっとわかりやすく言うと、”謎々の問題部分を作る”。
表から裏を想起させる方法は、
ほかの言葉遊びに比べると、最初作り方をのみ込むまでちょっと戸惑う方が多い物者附。
本稿では古今亭駒子師プロデュース『2022秋スピリッツ』互選会で柳家小ゑん宗匠が指導してくれた物者附を詠むうえでの注意点を、筆者なりにまとめてみました。
本稿では古今亭駒子師プロデュース『2022秋スピリッツ』互選会で柳家小ゑん宗匠が指導してくれた物者附を詠むうえでの注意点を、筆者なりにまとめてみました。
いったんコツがわかれば、とても深くて楽しい物者の世界。
黒猫こまちの新作イラストもありますので、雑俳にはご興味ない方もざっとお目通しいただけたら幸いです。
黒猫こまちの新作イラストもありますので、雑俳にはご興味ない方もざっとお目通しいただけたら幸いです。
※以下で取り上げる作品は全て選に入ったもので、病い句(ルール違反の句)ではありません。
あくまでも”ここにもっと留意すれば、さらに物者附作品としての完成度が上がるよ”という小ゑん宗匠のアドバイスを受けた句ということで、ご紹介させていただきます。
あくまでも”ここにもっと留意すれば、さらに物者附作品としての完成度が上がるよ”という小ゑん宗匠のアドバイスを受けた句ということで、ご紹介させていただきます。
物者附注意点①
「表」が立つように
「表」が立つように
2022秋スピでの物者附の題は、「丸くてある・するものは」。
”丸い”と言われて思いつく人が多いであろう「月」を裏にした句が、今回も沢山出ていました。
”丸い”と言われて思いつく人が多いであろう「月」を裏にした句が、今回も沢山出ていました。
そのうちの一句
「兎のお餅」。
かわいらしい句ですね。
裏はもちろん、「満月」。
「兎のお餅」。
かわいらしい句ですね。
裏はもちろん、「満月」。
ただ小ゑん宗匠曰く、惜しいのはこの句の表が今ひとつ立っていないこと。
表は本来、特別な説明なしで誰にとっても意味が通じる文句になっていなければいけません。
「兎のお餅」はスムーズに裏の意「満月」を想起させることができていますが、
と聞かれたらちと返答に困る。
表は本来、特別な説明なしで誰にとっても意味が通じる文句になっていなければいけません。
「兎のお餅」はスムーズに裏の意「満月」を想起させることができていますが、
と聞かれたらちと返答に困る。
実際に兎の形をしていたり兎のキャラクターが宣伝していたり、「兎」が付く名前の店が製造・販売していたりするお餅で。
 それが全国区の有名な商品であれば「兎のお餅」はじゅうぶんに表が立っている句になりますが、現時点では”ちょっと弱い”ということですね。
それが全国区の有名な商品であれば「兎のお餅」はじゅうぶんに表が立っている句になりますが、現時点では”ちょっと弱い”ということですね。

満月を裏・表に兎を使うのなら、たとえばこんな句も考えられるかと。
 「満ちたりた兎」。
「満ちたりた兎」。

物者附注意点②
言い換えにならないよう
言い換えにならないよう
やはり月を裏にした句で
「ススキの向こう側」
というのもありました。
裏は「中秋の名月」。
「ススキの向こう側」
というのもありました。
裏は「中秋の名月」。
”ススキの向こうにあるものはな~んだ。ヒントは丸いものだよ”と聞かれて、”わかった、廃工場のガスタンク!”と答える人はまずいないでしょうし。
「ススキの向こう側」も日本語として意味は通ります。
「ススキの向こう側」も日本語として意味は通ります。
ただこの句も惜しむらくは、表が「ススキの向こう側に見えるもの」=「ススキを飾って見る中秋の名月」という説明の方に寄ってしまっている。
これだと表と裏、言い方が違うだけで表しているのは同じ物事。
こういう句は雑俳物者附として”間違い”ではありませんが、”ビタ”(表と裏の意が近すぎる)といって高得点にはなりにくいそうです。
これだと表と裏、言い方が違うだけで表しているのは同じ物事。
こういう句は雑俳物者附として”間違い”ではありませんが、”ビタ”(表と裏の意が近すぎる)といって高得点にはなりにくいそうです。
この句をヒントに、ススキを活かして満月を詠むのなら。
うまくはありませんけど、こんなのはいかがでしょう。 「見下ろしたすすきの」。
「見下ろしたすすきの」。
うまくはありませんけど、こんなのはいかがでしょう。

JR札幌タワー展望室から臨む大通り・すすきの方面の夜景は、北海道の有名観光スポットになっていますから。
なんとかギリギリ、表が立つ…かな?
なんとかギリギリ、表が立つ…かな?
物者附注意点③
お隣さんに気をつけろ!
お隣さんに気をつけろ!
筆者が採らせていただいた字物者の句で、こういう作品が。
「里で見た犬」。
「里で見た犬」。
これを見た瞬間
という効きを思いつき、勇んで抜かせてもらったのですが…。
残念ながらこの句は、「おとなり」といって物者附の中では評価が下がってしまう詠み方。
という効きを思いつき、勇んで抜かせてもらったのですが…。
残念ながらこの句は、「おとなり」といって物者附の中では評価が下がってしまう詠み方。
「里で見た犬」の裏はもちろん、『南総里見八犬伝』中の”八つの霊玉”。
 一見(きれいに決まってるじゃないの、どこがいけないの?)と思いますが…。
一見(きれいに決まってるじゃないの、どこがいけないの?)と思いますが…。

雑俳物者附では、
という約束ごとがあります。
という約束ごとがあります。
①表「里で見た犬」→②中継点「里見八犬伝」→③裏「八つの霊玉」と間にワンクッション(犬だけに)挟むこういう句は、よほどうまくできていないかぎり選には入らない。
もし題が「丸いもの」でなく「芝居であるするもの」「映画であるするもの」だったら、「里で見た犬」は文句無しの秀句と言えるでしょう。
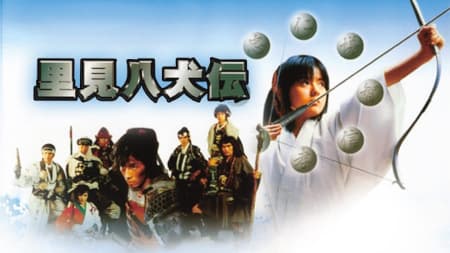
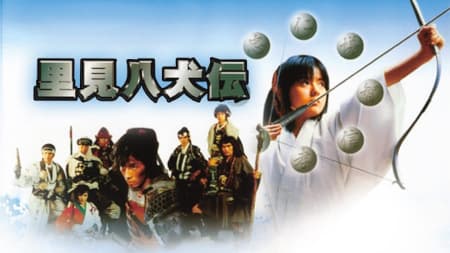
物者附注意点④
ぐるりと戻っていないか?
ぐるりと戻っていないか?
実は今回筆者がいったん抜いておきながら、悩んだあげく選外にした句があります。
「軍艦の乗組員」。
裏は、イクラですね。
「軍艦の乗組員」。
裏は、イクラですね。
シャリの上のイクラが”乗組員”という表現が面白く、幼い子どもたちが回転寿司でイクラ軍艦巻喜んで食べていたのも思い出し。
という効きを付けて採らせていただいたのですが…。
という効きを付けて採らせていただいたのですが…。
ふと、(これって、戻っちゃってる句なんじゃないの?)と心配になってきました。
以前「高くてあるするものは」という題の時、「惑わせたスター」という句が出たことがあります。
表は説明するまでもなし、裏は「惑星」なのですが…。
表は説明するまでもなし、裏は「惑星」なのですが…。
芸能界などで華々しく活躍する人を「スター」と呼ぶのは、その輝きを天上の星になぞらえているから。
つまりこの句の表で詠まれている「スター」の語源は「星」であり、もともと両者は同じ意味。
こういうのは”戻ってしまう”といい、やはり雑俳物者附では位が下がる要因に。
つまりこの句の表で詠まれている「スター」の語源は「星」であり、もともと両者は同じ意味。
こういうのは”戻ってしまう”といい、やはり雑俳物者附では位が下がる要因に。
洒落ではありませんがここで話を「軍艦の乗組員」に戻します。
寿司の「軍艦巻」は、その見た目が船の軍艦に似ているから来たネーミング。
だから戻ってしまっている句ではないかと気を揉んだのですが、小ゑん宗匠に確認したところ”絵物者としてちゃんと成立している句”でOKだとのこと。
だから戻ってしまっている句ではないかと気を揉んだのですが、小ゑん宗匠に確認したところ”絵物者としてちゃんと成立している句”でOKだとのこと。
小さい軍艦巻と本物の大きな軍艦ではイメージがまるで違い、「軍艦とそれに似ている寿司の巻物」の言葉としての関係性が「スターと星」ほど密ではないからということなのでしょうか。
そういったわけであらためて、
「軍艦の乗組員」。 謹んで、選に入れさせていただく次第です。
謹んで、選に入れさせていただく次第です。
「軍艦の乗組員」。

物者附注意点⑤
勢いで表に飛び出すなかれ
勢いで表に飛び出すなかれ
「祝日に出た太陽」。
筆者は裏が「初日の出」だと思っていたら、作者の方の意は「日の丸の旗」。
筆者は裏が「初日の出」だと思っていたら、作者の方の意は「日の丸の旗」。
今は比較的少なくなりましたが、「旗日」というくらいで昔は休日になると玄関先に日本の国旗を掲げるお宅がよく見られたものです。
 こまちは、
こまちは、
毎日が旗日で休みだろ?

毎日が旗日で休みだろ?
句想をうかがい(なかなかいい裏だな)と感心したのですが、この句の残念ポイントは「太陽」というそれ自体丸いものが先に表へ出ているところ。
「日の丸の旗」をどう裏に隠そうかという方に注意が行き過ぎて、つい勢いで表に「太陽」を詠みこんでしまったということでしょうか。
「日の丸の旗」をどう裏に隠そうかという方に注意が行き過ぎて、つい勢いで表に「太陽」を詠みこんでしまったということでしょうか。
「祝日に出た太陽」が、”せっかくのお休みの日、お天気で良かった”という意でしたら。
「晴れだった休日」
なんて表もありかなと。
「晴れだった休日」
なんて表もありかなと。
民俗学には「褻(ケ=日常)」に対して、「晴(ハレ=儀礼や祭事などの非日常」という概念があります。
毎週巡って来る日曜と違ってただの休みじゃない、 特別な意味のあるハレの祝日は国旗掲揚で祝う…。
だから「日の丸の旗」という裏に、なんとか持っていけないかなぁ。
毎週巡って来る日曜と違ってただの休みじゃない、 特別な意味のあるハレの祝日は国旗掲揚で祝う…。
だから「日の丸の旗」という裏に、なんとか持っていけないかなぁ。

物者附は
わかれば面白い!
わかれば面白い!
以上の駄文ではなかなか伝わらないかもしれませんが、とにかく本稿で申し上げたいのは「物者附は、コツがわかってくると面白い!」
その魅力の一つが、
という、ほかの雑俳の題にはない深さ面白さ。
という、ほかの雑俳の題にはない深さ面白さ。
本シリーズ次回はその件について、実例ご紹介しながら綴らせていただきます。
※『2022年秋スピリッツ』物者附作品一覧と絵物者・字物者についての簡単な解説は
をご覧ください。
をご覧ください。
ご精読ありがとうございます。
ぜひまた、ご訪問くださいませ。
入船亭扇治拝
ぜひまた、ご訪問くださいませ。
入船亭扇治拝




